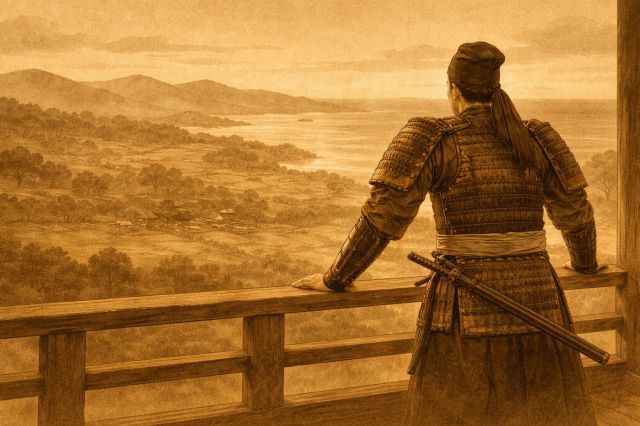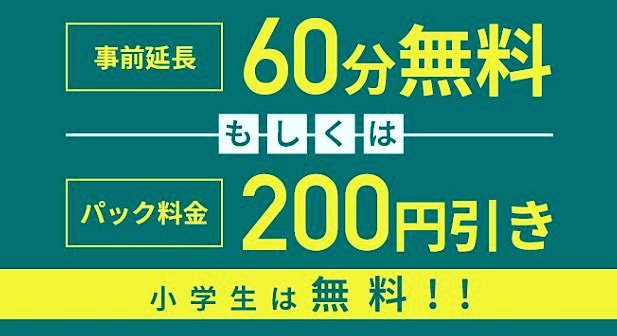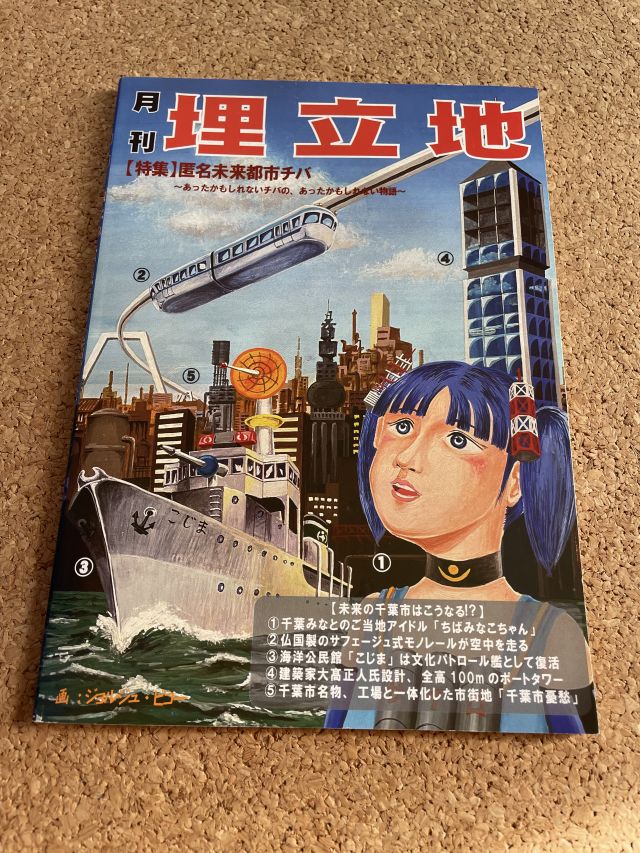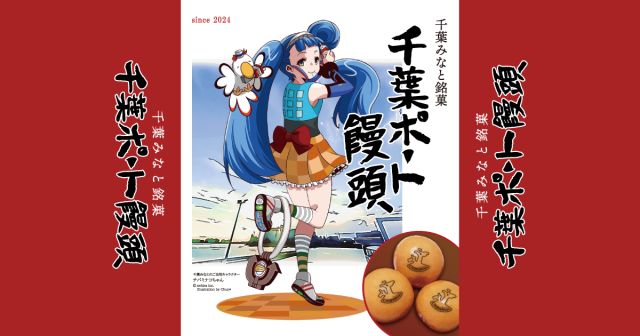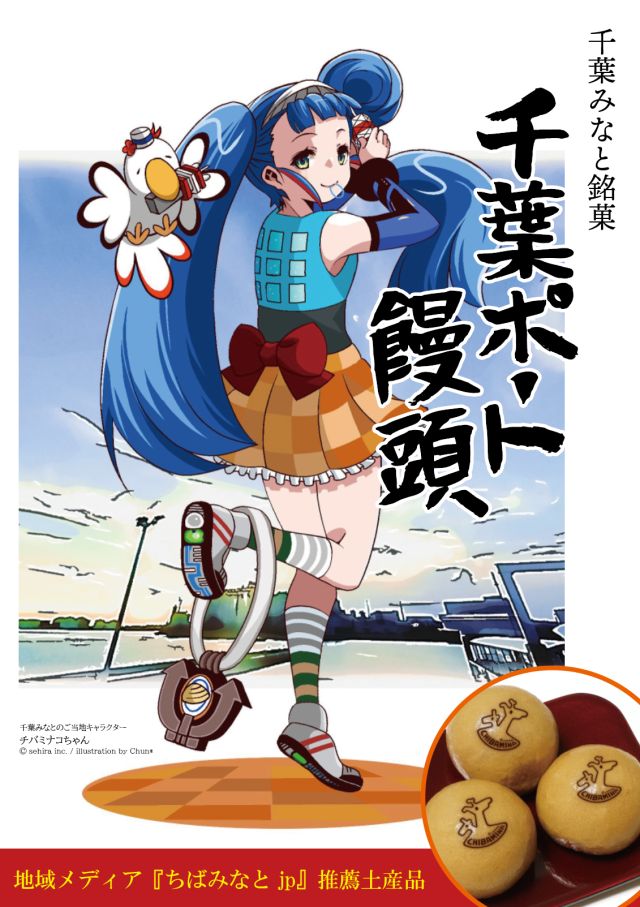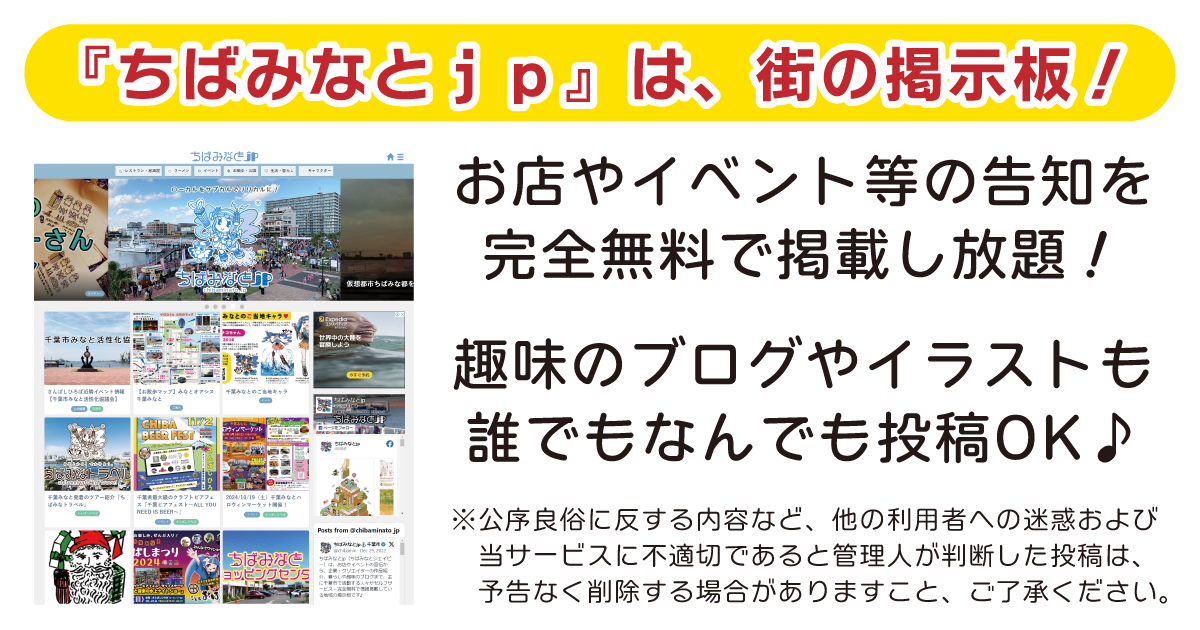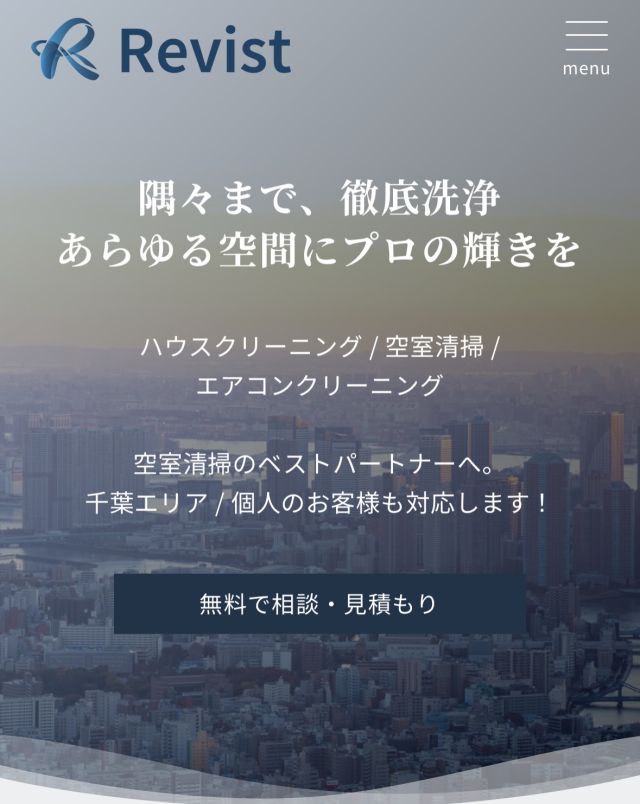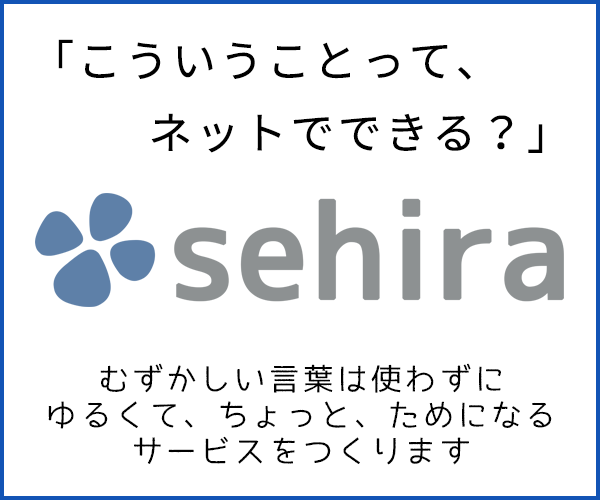来春自転車にも青切符【稲毛新聞2025年10月号】
670
2025/10/2
2026年4月1日から自転車の青切符制度が施行される。この青切符、比較的軽微な交通違反に交付される「交通反則告知書」の通称で、用紙が青いことから青切符と呼ばれている。
現在自転車における違反行為は「注意」で済んでいるが、施行以降16歳以上の人は青切符による反則金が生じることになる。スマホを操作しながらの運転や逆走、無灯火など今でも日常よく見かける運転の多くが違反となる。
現在自転車における違反行為は「注意」で済んでいるが、施行以降16歳以上の人は青切符による反則金が生じることになる。スマホを操作しながらの運転や逆走、無灯火など今でも日常よく見かける運転の多くが違反となる。
自転車利用者の交通ルール理解が必要

●ながら運転…携帯電話の使用(反則金1万2千円)/よく見かける光景だが、事故事例も多く危険な行為と言えるだろう。
●信号無視…信号無視や横断歩道以外での横断(同6千円)/自転車だと周辺の状況により安易な気持ちで赤信号を無視してしまうことも少なくないのでは。
●逆走・歩道走行…(同6千円)/現状最も多いケースなのではないか。原則自転車は道路を走行するのがルール。歩道走行が許されるのは「歩道通行可」の標識がある場合など限定的。狭い道など危険な場合もあるが、今後は青切符の対象となる。逆走に関しては現状気にして走行している人は少ないのではないか。街中で見かけるケースは非常に多い。車を運転していると正面左側から対抗自転車が走ってくる。狭い道、交通量の多い道では危険極まりない。
●並進走行…2台並んでの走行(同3千円)/並んで会話しながら走行している光景を見かけるが、幅をとり危険な運転だ。
●2人乗り…(同3千円)/子供を乗せるチャイルドシート等のルールは別だが、2人乗りも今後は取り締まりの対象になる。
●イヤホン使用・傘さし運転…(同5千円)/これも日常の光景だが、イヤホンにより周辺の音が聞こえない、傘により視認性が落ちる。最も危険な運転なのではないか。
●夜間無灯火…ライトを点灯せずに運転(同5千円)/夜間の無灯火は周辺の車、歩行者にとっては直前まで目視できず事故につながりやすい危険運転だ。
車の運転免許を所持している人は、教習所や免許更新の時にある程度の知識は得られるだろうが、そのような経験がない人や学生などは違反の意識すら乏しいことが想像できる。ある40代の女性は「普段車を運転しますが、ルールを無視した自転車は非常に多いと思います。取締りは必要だと思います」と話している。また30代男性は「ルールの徹底と周知が大事なのでは」と。確かにルールの認識が乏しい自転車利用者にとっては、違反の意識も薄い。警察や行政による啓発やルールの徹底、また自転車を利用する側も今後はこれらに該当しないためにも交通ルールを正しく理解することが必要になる。自転車ルールブックは警視庁のホームページで見ることができる。
●信号無視…信号無視や横断歩道以外での横断(同6千円)/自転車だと周辺の状況により安易な気持ちで赤信号を無視してしまうことも少なくないのでは。
●逆走・歩道走行…(同6千円)/現状最も多いケースなのではないか。原則自転車は道路を走行するのがルール。歩道走行が許されるのは「歩道通行可」の標識がある場合など限定的。狭い道など危険な場合もあるが、今後は青切符の対象となる。逆走に関しては現状気にして走行している人は少ないのではないか。街中で見かけるケースは非常に多い。車を運転していると正面左側から対抗自転車が走ってくる。狭い道、交通量の多い道では危険極まりない。
●並進走行…2台並んでの走行(同3千円)/並んで会話しながら走行している光景を見かけるが、幅をとり危険な運転だ。
●2人乗り…(同3千円)/子供を乗せるチャイルドシート等のルールは別だが、2人乗りも今後は取り締まりの対象になる。
●イヤホン使用・傘さし運転…(同5千円)/これも日常の光景だが、イヤホンにより周辺の音が聞こえない、傘により視認性が落ちる。最も危険な運転なのではないか。
●夜間無灯火…ライトを点灯せずに運転(同5千円)/夜間の無灯火は周辺の車、歩行者にとっては直前まで目視できず事故につながりやすい危険運転だ。
車の運転免許を所持している人は、教習所や免許更新の時にある程度の知識は得られるだろうが、そのような経験がない人や学生などは違反の意識すら乏しいことが想像できる。ある40代の女性は「普段車を運転しますが、ルールを無視した自転車は非常に多いと思います。取締りは必要だと思います」と話している。また30代男性は「ルールの徹底と周知が大事なのでは」と。確かにルールの認識が乏しい自転車利用者にとっては、違反の意識も薄い。警察や行政による啓発やルールの徹底、また自転車を利用する側も今後はこれらに該当しないためにも交通ルールを正しく理解することが必要になる。自転車ルールブックは警視庁のホームページで見ることができる。
このまとめ記事の作者
ログインしてコメントしよう!